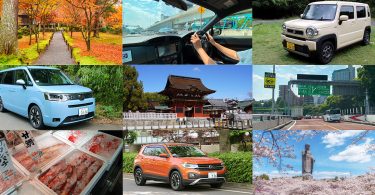あの標識って、どんな意味だったかな? たまに見かけるけど、思い出せない……。そんな経験、皆さんもあるのでは?
事故を起こさないことはもちろん、交通の流れを乱さないためにも大切な交通ルール。けれど、中には忘れられやすいものや、曖昧に覚えてしまいがちなものがあります。そこで、今回はおさらいしておきたい交通ルールを「◯×クイズ」にしました。ぜひ、全問正解を目指してチャレンジしてみてください!
<目次>
・問題(1) 信号機のない横断歩道
・問題(2) 青信号の意味
・問題(3) ゼブラゾーンへの進入
・問題(4) 後部座席でのシートベルト
・問題(5) スクールゾーンの制限速度
・問題(6) オレンジのセンターライン
・問題(7) スマホと「ながら運転」
・問題(8) カーシェア車両の故障
・問題(9) 「駐車禁止」と「駐停車禁止」
・問題(10) 一方通行をバックしたら
・問題(11) あおり運転
・問題(12) 運転するときの履物
・曖昧なルールをおさらいして安全運転を
問題(1)信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら、一時停止しなければならない

正解:○
道路交通法(第38条1項)により、信号機のない横断歩道を渡っている歩行者、もしくは渡ろうとしている歩行者を見かけたら、走行中のクルマは一時停止し、歩行者の横断を妨げないようにするよう定められています。これに違反すると「横断歩行者等妨害等違反」の罰則を受けます。
しかし、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)の「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査(2022年)」報告によると、およそ60%のクルマが一時停止をせずに通過してしまったそう。
横断歩道はもちろんですが、そうでない場所であっても道路を横断しようとしている人がいたら一時停止をし、互いが安全になれる運転を心がけましょう。
<関連リンク>
>>>警察庁「横断歩道は歩行者優先です
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
>>>JAF「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査(2022年調査結果)」
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/survey-report/2022-crosswalk
問題(2)赤信号の意味は「止まれ」。では、青信号の意味は「進め」である
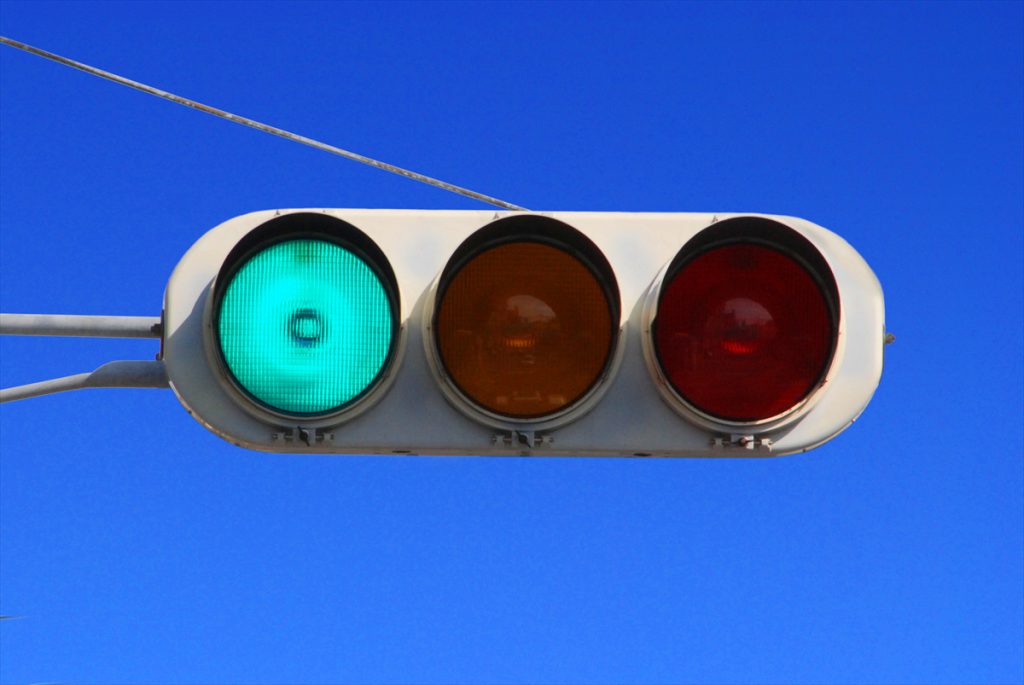
正解:×
青信号が意味するのは「進め」ではなく、「進むことができる(直進し、左折し、右折することができる)」です。
道路上に歩行者がいたり、交差点内にほかのクルマが進入していて通行できないなど、危険が予測される場合は、停止したままでも問題ありあせん。青信号になったのち、周囲の安全を確認して問題がなければ、すみやかに進んで交通渋滞を作らないよう心がけましょう。
問題(3)右左折車線の手前などに印される「ゼブラゾーン(斜線の入った場所)」には進入してはいけない

正解:×
ゼブラゾーンは「導流帯」と呼ばれ、「クルマの安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所」であることを示しています。ゼブラゾーンを走行すること自体は、法令上の違反行為には該当しません。
ですが、ゼブラゾーンが設置されるのは、主に交通状況から車線を一時的にしぼるなどの誘導が必要と判断された場所です。進入せずに走行することで、スムーズに車線の変更が行えるようになっています。
自身の安全や円滑な交通の流れのためには、可能な限りゼブラゾーンに進入しない運転がよいといえるでしょう。
問題(4)一般道でも後部座席の乗員はシートベルトをしなければならない

正解:○
運転席と助手席のシートベルト着用義務が定められたのは、1992年。それから長らく、後部座席のシートベルト着用は「着用が望ましいが、着用していなくとも罰則はない」という努力義務にとどまっていましたが、2008年6月の道路交通法改正により、すべての座席での着用が義務付けられました。
後部座席のシートベルト未着用による罰則の発生は、高速道路と自動車専用道路のみ。一般道路では具体的な罰則はなく、口頭による注意にとどまります。
とはいえ、罰則がなくても立派な違反行為です。場合によって事故が発生した際の過失相殺に影響しますし、なにより安全に関わります。どうしても着用できない特別な事情がない限り、きちんとシートベルトを着用し、もしもの事態に備えましょう。
問題(5)スクールゾーンでは時速30km以下で走行しなければならない

正解:×
1972年より運用の始まったスクールゾーン。幼稚園や小学校を中心とした半径約500メートル内の通学路が対象になります。スクールゾーンであっても特別な速度制限を設けることはなく、その道路の交通規制に準じます。
道幅増員が4.0メートル未満の場合は、通学時間帯に限り「歩行者自転車専用道路」の指定を実施する場合も。指定時間内は車両通行禁止となり、区間内を通行できるのは通行許可証を所有している車両や緊急車両、道路維持作業車両などに限られます。それ以外のクルマは通行すると罰則を受けるので注意しましょう。
問題(6)オレンジのセンターラインは「追い越しのためのはみ出し禁止」である

正解:○
センターライン(中央線)には大別して「白線の実線」と「白線の破線」、そして「オレンジ(黄色)の実線」の3種類(及び、それらが複合した線)があります。オレンジのセンターラインは「追い越しのためのはみ出し禁止」を意味しており、これに違反すると罰則の対象に。駐車しているクルマや工事区間、路上の障害物を避ける行為は「追い越し」ではないので、はみ出して通行することができます。
ちなみに、白線の実線は「原則としてはみ出しての通行は禁止。ただし、はみ出さなければ追い越しをしてもよい」。白線の破線は「前走車の追い越しや駐車車両を避ける際、はみ出すことができる」ことをあらわしています。
<関連記事>
>>>道路のセンターラインの種類と意味をおさらいしよう
https://blog.careco.jp/14468/
問題(7)運転中、スマホのカーナビアプリなら操作しても「ながら運転」にならない

正解:×
「ながら運転」とは、ドライバーが「スマホで電話をしながら運転」や「テレビを視聴しながら運転」など、運転操作とは関係のない行動を行いながらクルマを走行させる行為を指し、「道路交通法第71条第5号の5」により明確に禁止されています。
この道路交通法を簡単に説明すると、ドライバーは「クルマが停止しているとき」と「怪我人や病人の救護時」「緊急事態時」をのぞき、「カーナビやスマホによる通話」と「カーナビやスマホ画面の注視」を禁じるといったものです。
ナビアプリの使用自体は違反に該当しません。ですが、運転中の操作は「画面を注視する行為」となるため違反となります。ながら運転は直接、事故に繋がる危険な行為です。スマホは視界を妨げない位置に固定し、ナビアプリの設定は走行前、あるいはクルマを安全な場所に止めてから行いましょう。
問題(8)トンネルに入り、オートライトが点灯。片方のヘッドライトが切れているのに気付いたが、カーシェア車両なのでそのまま運転した

正解:×
道路交通法第62条により、「車検に適合しない状態のクルマは、運転してはならない(運転させてはならない)」と定められています。問題のようなヘッドライトの点灯不良は「整備不良(尾灯等)」に該当し、罰則の対象です。クルマの所有者は関係なく、カーシェア車両やレンタカー、社用車など、誰のクルマであっても運転していたドライバーが罰則を受けます。
カレコのクルマを利用中にライト類の点灯不良を見つけた場合、安全な場所に停車し、カレコ・サポートセンターへの連絡をお願いします。また、利用開始時にすべてのライトが正常に点灯するかの確認も、あわせてお願いいたします。
<関連記事>
>>>パンクにバッテリーあがり……ドライブ中に「トラブル」が起きたら? その対処法
https://blog.careco.jp/18781/
問題(9)この標識は「駐停車禁止」である

正解:○
駐停車禁止の標識が提示されている場所は、原則として緊急時や警察官、信号による指示がない場合、駐車も停車も行えません。よく似た標識に「駐車禁止」があります。

駐車禁止の標識が提示されている場所は駐車を行えませんが、停車は認められています。停車とは「人の乗り降りのための停止」「5分以内の荷物の積み卸しのための停止」を指します。5分以内であっても「ドライバーがクルマから離れ、ただちに運転できない状態」は、停車ではなく駐車とみなされるので注意が必要です。
問題(10)間違って一方通行の道路に反対方向から進入してしまったので、急いでバックで戻った

正解:×
一方通行の道路に逆から進入してしまった時点で、すでに通行禁止違反です。すみやかにクルマを移動させる必要はありますが、急いでバックで戻る行為は大変危険です。誤って一方通行の道路に反対方向から進入してしまったら、ハザードを点灯して停車し、周りのクルマや歩行者に誤って進入してしまったことを伝えます。
周囲の状況からそのまま進むか、転回(Uターン)を行うか、バックして戻るかを判断します。先にも記しましたが、慌ててバックや転回(Uターン)するのは大変危険な行為なので、絶対にしないでください。可能ならば同乗者や周囲の人に誘導してもらい、歩行者や自転車に細心の注意を払って、一方通行区間からクルマを移動させましょう。
<関連記事>
>>>駐停車禁止に時間指定……忘れがちな標識をおさらい
https://blog.careco.jp/15434/
問題(11) 前のクルマの速度が遅かったので、車間距離を詰めた

正解:×
特に交通量の多い都市部の道路を走行していると、車間距離が短くなりがちです。余裕を持ち、「少しあけすぎかな?」と思うぐらいがちょうどよいでしょう。2020年6月に道路交通法が改正され「あおり運転(妨害運転)」は、厳罰化の対象となりました。あおり運転の加害者にも被害者にもならないように、今一度、違反内容をおさえておきましょう。
あおり運転違反に該当するのは以下の通りです。
・通行区分違反(対向車線からのはみ出しや逆走)
・車間距離を詰める
・明らかに妨害行為と思われる急ブレーキ
・不必要なクラクション
・急な進路変更(割込み)
・ハイビームをつけたままの長時間の走行やパッシングを繰り返す
・左側から急に追越す行為
・幅寄せや蛇行運転、急にスピードを変える
・高速道路での最低速度違反
・高速道路での駐停車
<関連記事>
>>>あおり運転「しない・させない」安全運転のポイント
問題(12) 急ぎの用事があったのでサンダルのまま運転した

正解:×
道路交通法では「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定めています。そのため、脱げやすいサンダルでの運転は道路交通法違反にあたる可能性があります。
また、各都道府県の公安委員会が定める細則(公安委員会遵守事項)にも、運転時の履物について明確な基準が設定されています。お住まいの地域や旅行先の規定を調べておくと安心です。
東京都の場合では、道路交通規則第8条により「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」となっています。特にサンダルを履く機会が多い夏場は気をつけましょう。
曖昧なルールをおさらいして安全運転を!
交通ルールを守ることは自身や同乗者の安全を守るだけでなく、歩行者を守り、交通事故の原因となるリスクを低減させるもの。忘れてしまったルールや曖昧になってしまったルールがあったら、そのままにせず、いま一度、確認しておきましょう。より一層の安全で、同乗者が安心してくれる運転を心がけたいですね。
>>>さらに「ドライブの知識」の記事を見る
https://blog.careco.jp/category/knowledge/
<カレコについて>
ご利用の流れ https://www.careco.jp/flow/
料金について https://www.careco.jp/plan/
車種ラインアップ https://www.careco.jp/car/
<最新情報はカレコ公式SNSで>
Facebook、Twitter、Instagram、LINE
記事内容は公開時のものです。変更になる場合があります。